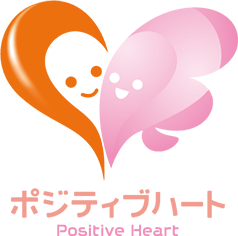兼峯 大輔
福岡県出身。高校は大濠高校で駅伝部に入部。800Mの選手(自己記録1分54秒)としてインターハイに出場する。
平成7年福岡大学経済学部に進学。
平成11年3月に卒業。教員免許取得(高校地理歴史)
昭和51年 4月
大手飲料メーカーに就職する。
平成16年
結婚と同時に義父の経営する介護事業所に転職する。
そこで介護現場で「人」に関する問題が多いことに直面し、社会保険労務士になることを決意。平成18年合格。
平成20年
介護事業に特化した社労士事務所エール労務サービスを開業。
同年TAC社労士講座講師を務める。
視覚障がい者のための音声ダビング就業規則を作成し業界で話題となり好事例として
社労士会の会報誌に掲載される。
平成22年
日本介護福祉グループ取締役就任。小規模デイサービスのコンサル事業に着手。全国800事業所(九州88事業所)の介護サービスの開設に携わる。
また介護業界の人手不足の解消と世代間交流の場を提供する「介護と保育」の融合事業を株式会社グローバルブリッジ社とコラボして九州に3か所手掛け話題になる。
平成25年
一般社団法人九州介護協会副理事長に就任。
介護業界の質の向上、行政と民の橋渡し役として勉強会を主催また、外国人労働者の受け入れの問題提議や若い人たちが介護業界へ魅力を感じてくれるための様々な広報活動を企画し業界の人財不足解消へ尽力する。
平成26年
FC本部を構築するコンサル会社、株式会社ディライト・ジャパンの執行役員に就任。専門分野は介護・障害・保育・整骨院などの制度ビジネスのFCのモデル構築。
放課後等デイサービスや就労支援事業所を運営する株式会社 空色の顧問に就任し、
放課後等デイサービス10ヵ所、就労支援1か所の開設に関わる。
平成27年
全国社会保険労務士会連合会のオフィシャルなプロジェクト「介護労務管理研修」のプロジェクトチームに40000人いる社労士の中から選抜され、介護事業に特化した社労士を養成する講座を担当し全国で講演活動をおこなう。近年は介護だけでなく障がい者支援、保育支援を含む、総合的な福祉モデルの提唱をし、全国で講演活動を行う。
平成28年
社労士法人 ブレインスターと合併社労士事務所としては希少な31名の専門家集団に成長させている。
平成28年 8月15日
ポジティブハート株式会社 設立
平成29年
城南区に三幸保育園 開園
これを機に講演活動も保育業界向けに実施。29年7月に保育協会にて「今後の法改正と多様な働き方改革への対応」というテーマで講演。
主な講演・研修実績
■「これからの総合福祉モデルの構築」アジアメディカルショー
■「保育と介護の融合で社会が変わる」グローバルブリッジ
■「処遇改善加算と助成金活用」介護労働安定センター
■「知らないと損する助成金」日本政策金融公庫・福岡市スタートアップカフェ
■「介護事業の労務管理」リコージャパン
■「社会福祉事業のマネートラブル解決法」佐賀市社会福祉協議会
■「管理職のためのセクハラパワハラ防止研修」コカコーラウエストジャパン
■「セクハラ・パワハラ研修」JA熊本
■「介護労務管理研修」福岡県介護保険課
■「今後の法改正と多様な働き方改革への対応」 保育協会
事業への想い
介護業界に特化した社会保険労務士として起業しました。
クライアントの多くは介護や障がい施設、医療機関、そして幼稚園や保育園です。
保育園を開園してからは労務管理に力を入れ、保育協会の研修でも社会保険労務士という立場で講演させていただきました。
講演内容は「働く」という観点から、これらの社会福祉事業の専門職の処遇や労働環境や、キャリアアップの仕組みの必要性を伝えました。
以前から研修講師やコンサルタントと共に「質の高い社会福祉サービス」の実現をめざし、社会保障制度の啓蒙活動やセミナー・講演活動の積極的な活動も実務を通して理解が深まりました。
三幸保育園を開園してからは、保育事業への情熱と社会的な意義を再認識したところでございます。
少子化問題、待機児童の問題、労働力人口の減少、日本の国力が低下する中、これらの問題を解決するには働く保育士の処遇の改善と地位向上が不可欠だと感じております。保育や介護などの福祉職が仕事の大変さにも関わらず、福祉という観点から利益追求が懸念され、直接的に「賃金に反映されない風習」があるのを社会保険労務士の仕事を通じて感じてきました。しかし、企業努力によって職員の処遇を改善し、「生き生きと働く」環境を実現しているクライアントもたくさん見てきました。
また、私自身も保育園の経営を通じて、保育士の幸せを実現できるように努力を惜しまず取り組んでまいりました。
今後は、新しい社長に法人の舵取りを任せ、私は今までの知識・経験を活かしアドバイザーとしてみんなのサポート役に努めてまいります。